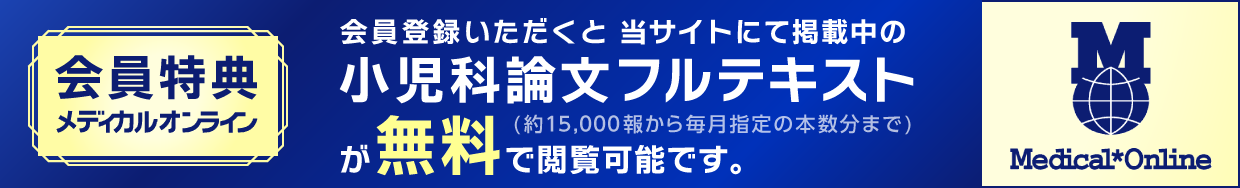掲載日:
健康診断結果報告書や患者サマリーの実装を目指す――電子カルテ情報共有サービス
厚生労働省(以下、厚労省)は、9月11日に開催された第18回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(以下、ワーキンググループ)で、本人および事業者、保険者等に送られる「健康診断結果報告書」を電子カルテ情報共有サービス(仮称)稼働時の実装を目指すことを提案した。
電子カルテ情報共有サービス(仮称)は、オンライン資格確認等システム基盤を活用し、電子カルテ情報等を登録することで、1)文書情報を医療機関等が電子上で送受信できる、2)全国の医療機関等で患者の電子カルテ情報(傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査・処方の6情報)を閲覧できる、3)本人等が、自身の電子カルテ情報(6情報)を閲覧できる――という主な3つの仕組みからなるサービス。政府が6月に決定した医療DX推進に関する工程表によると、2024年度中に電子カルテ情報の標準化を実現した医療機関等から順次運用を開始する予定だ。