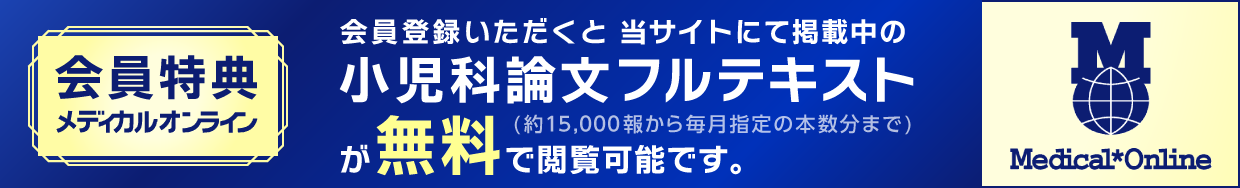治療が必要な再活性化未熟児網膜症における網膜脈管形成の特徴とラニビズマブ再注入後の臨床転帰。
DOI:10.1038/s41598-024-66483-2
アブストラクト
本研究の目的は、抗血管内皮増殖因子(抗VEGF)注射後の網膜血管の状態が、治療を必要とする再活性化未熟児網膜症(ROP)のリスクを予測するのに役立つかどうか、またそのような場合にラニビズマブ注射を繰り返すことが有効かどうかを明らかにすることである。2021年1月から2022年12月までにラニビズマブ単剤療法を受けた乳児24例(43眼)をレトロスペクティブに検討した。全眼を非治療期ROPまたは治療期ROPに分類した。治療時のROPの状態、プラス疾患の消失に要した時間、治療後4週と8週の血管新生の程度を解析した。網膜の側脈管形成の程度は、連続眼底画像で円板-窩間距離(DF)単位と円板直径(DD)を用いて測定した。ラニビズマブ治療後、治療を必要とするROPの再発が乳児6例(25.0%)、10眼(23.3%)にみられた。平均再治療間隔は9.0±3.3週(範囲4~16)であった。再治療を行ったROP群では、一次注射後のプラス疾患の消失に要した時間は対照群と比較して長く(13.3日 vs 5.2日)、平均ROP退縮時間は3.4週であった。退縮したROPのすべての眼は、注射後4週目に元の部位から0.5DF未満の網膜血管形成を示した。ROP退縮例の90%において、注射後8週目の血管新生範囲は元のROP部位から1DF以内であり、全例で後Ⅱゾーン領域での再活性化が認められた。再治療群の網膜新生血管の広がりは、注射後4週および8週でそれぞれ平均0.7DD(対1.7DD)および1.3DD(対3.3DD)であった。ラニビズマブ再投与後、硝子体牽引を伴う再活性化1例のみが巣状網膜剥離に進行したが、他の全例は末梢血管の発達とともに退縮した。8週間以上経過しても網膜血管の発達が遅れているということは、治療が必要な再活性化ROPの可能性が高いことを示しているのかもしれない。硝子体牽引がなければ、ラニビズマブ再注入は治療を要する再活性化ROPの治療に有効であると考えられる。